2025.04.10
カーボンニュートラルに向けた協創事例6選|効果を高めるためのポイントも 0

目次
地球温暖化対策は各国共通の課題として認識されており、国内の各企業においても温室効果ガスの削減に向けて具体的な施策を講じることが求められています。しかし、自社だけでの取り組みで生み出せる効果には限りがあります。そこで注目したいのが、複数の企業がそれぞれの強みを持ち寄り、協力して取り組む「協創」というアプローチです。
そこで今回の記事では、カーボンニュートラルの実現に向けて企業ができることや複数社による協創の実例、効果を最大化するポイントまで詳しく解説します。
カーボンニュートラルとは

カーボンニュートラルとは、「温室効果ガスの排出量を全体としてゼロにすること」をいいます。
CO₂、メタン、一酸化二窒素、フロンガスなどの温室効果ガスは、地球温暖化の主な原因となっており、世界各国が排出量削減に向けて取り組んでいます。しかし、事業活動をおこなう上で温室効果ガスの排出を完全にゼロにすることは困難です。そこで、人間の活動によって排出される温室効果ガスと、自然界や技術による吸収・除去量を均衡させる「カーボンニュートラル」が実質的な目標とされているのです。
カーボンニュートラルの実現に向けて企業ができること

この章では、カーボンニュートラルの実現に向けて、企業ができる具体的な取り組みを2つご紹介します。
サプライチェーン全体でのエネルギー起源CO₂排出量削減
1つ目は、サプライチェーン全体でのエネルギー起源CO₂排出量の削減です。エネルギー起源CO₂とは、発電・運輸・産業などの事業活動で使用される化石燃料から発生するCO₂を指します。
具体的な取り組みは「電力分野」と「非電力分野」の2つに分けられます。
「電力分野」では、再生可能エネルギー由来の電力を供給する電力会社への切り替え、「非電力分野」では、水素やバイオマスなどの代替エネルギー活用の推進といった取り組みが考えられます。
また、設備面での改善として、LED照明への切り替えやモーターの回転数を制御して省エネを実現する「インバーターの導入による流量調整」も効果的です。さらに、省エネルギーセンターなどの公的機関のセルフ診断ツールも役立つかもしれません。このツールでは、調べたい事業所の業種・所在地(都道府県)・エネルギー使用量を入力するとCO₂排出量が計算でき、さらにエネルギー管理状況などの質問項目に回答すれば、同業他社とのエネルギー使用量の比較や、省エネポテンシャル、具体的な省エネ対策項目を提示してくれます。
再生可能エネルギーの活用
2つ目は、再生可能エネルギーの活用です。CO₂排出量が少なく、資源の枯渇を心配せず利用できることから、太陽光・風力・バイオマスなどに由来した電力の活用が注目されています。企業が再生可能エネルギーを導入する方法は、以下の2つです。
● 自社施設に太陽光パネルなどの発電設備を設置する
● 再生可能エネルギー由来の電力を電力会社から購入する
自社での設備導入は初期投資が必要ですが、長期的なコスト削減につながります。一方、電力購入は初期投資が不要で、比較的手軽に再生可能エネルギーを活用できます。自社の事業規模や設備投資の余力、事業所の立地条件などを考慮し、最適な導入方法を選択することが重要です。
カーボンニュートラルに複数の企業で取り組んでいる事例6選

カーボンニュートラルの実現に向けて、サプライチェーン全体でのCO₂排出量削減や再生可能エネルギーの活用などを複数社でおこなっている事例を6つ紹介します。
セブン&アイグループ×NTTグループ
セブン&アイグループとNTTグループは、店舗での再生可能エネルギー活用に向けて共同で取り組みを進めています。これにより、小売業界におけるCO₂排出量削減を実現し、環境への負荷を軽減することを目指しています。
具体的におこなっているのは、「自社店舗での発電」と「NTTグループとの連携による外部発電」の2つのアプローチです。前者においては、9,000店舗以上に太陽光発電パネルを設置しました。また後者においては、NTTグループと共同で遠隔地に設置した再生可能エネルギー発電所で発電し店舗へ送電する仕組みを導入し、2021年6月にセブンーイレブン41店舗での運用を開始しました。
これら2つのアプローチにより、セブン&アイグループは年間約7万トンのCO₂排出量削減を達成(2022年度実績)しました。この取り組みは、各店舗のエネルギー効率の向上にとどまらず、サプライチェーン全体での環境負荷の低減にも効果を発揮しており、企業が持続可能な成長を目指すための、ひとつのモデルケースになるといえるでしょう。
参考:2050年までにCO₂ 排出量を実質ゼロにするために。|株式会社セブン&アイ・ホールディングス
大日本印刷×OpenX Technologies
大日本印刷(DNP)とOpenX Technologies(OpenX)は、デジタル広告配信時のCO₂排出削減に向けて協業しています。デジタル広告では、データ処理や配信時のサーバー稼働により多くのCO₂が排出されます。この課題に対し、両社はOpenXの「Green Media Product」を活用して広告配信時のCO₂排出量を計測し可視化します。
また、広告の種類を年間約10%削減して通信量を抑制するほか、効果の高い媒体を優先する入札方式を採用することで、CO₂排出削減と効果的な広告配信の両立を目指しています。この取り組みは、環境負荷軽減に直結するだけでなく、持続可能なデジタルマーケティングを実現しているという点で、再現性が高い事例となっています。
参考:大日本印刷 OpenXと協業し、企業のデジタル広告取引におけるカーボンニュートラルを支援|大日本印刷株式会社
富士通×METRON
富士通とMETRONは、製造業のカーボンニュートラル実現を目指し、消費エネルギーを最適化するサービスを共同開発しました。
具体的には、富士通の製造業向けソリューションとMETRONのエネルギー管理プラットフォームを連携させ、工場内の設備や生産ラインごとのエネルギー使用量をリアルタイムで可視化し、過去のデータや外部環境要因を考慮したAI分析をおこない、エネルギー効率を最大化する生産スケジュールを自動で作成します。
2024年4月から日本で提供を開始し、将来的にはドイツでの展開も計画しています。製造業の持続可能性を高めるだけでなく、企業のESG(環境・社会・ガバナンス)目標の達成にも貢献するとして期待されているプロジェクトです。
参考:富士通とMETRON、エネルギーコスト削減と生産性向上の両立によりお客様のESG経営を支援するため戦略的提携|富士通株式会社
NEC×三井住友銀行×ゼロボード
NEC、三井住友銀行、ゼロボードの3社は、サプライチェーン全体でのCO₂排出量の可視化と削減を目的とした協業を行っています。
三井住友銀行の「Sustana」、NECの「GreenGlobeX」、ゼロボードの「Zeroboard」の3つのサービスをデータ連携させることで、サプライチェーン全体のCO₂排出量を可視化することで企業が抱える排出量削減課題を特定し、最適な削減ソリューションを提供します。また、ファイナンス支援を通じて、必要な投資へのアクセスを促進し、持続可能なプロジェクトの実行を後押しすることも可能になりました。
参考:NEC、三井住友銀行とカーボンニュートラル事業における協業に向けた基本合意契約を締結~サプライチェーン全体のCO₂排出量可視化を実現~|日本電気株式会社
出光興産×北海道電力×JAPEX
出光興産、北海道電力、JAPEXの3社は、北海道・苫小牧エリアにおいて、CO₂の回収・有効活用・貯留を行うCCUS事業の共同検討を開始しています。この取り組みでは、2030年度までに「ハブ&クラスター型CCUS事業」の立ち上げを目指しています。
ハブ&クラスター型CCUS事業とは、複数の排出源からCO₂を回収・有効活用するシステムです。実用化されると、1つの排出源からのCO₂回収・貯留に限定せず、地域の多くの排出源からCO₂を効率的に回収することで、社会全体の排出削減効果を高めることが可能になります。3社は現在この事業の実現に向けて、CO₂の排出・回収・輸送・貯留に関する技術検討と適地調査を進めています。
参考:出光興産、北海道電力、JAPEXの3社が北海道・苫小牧エリアにおけるCCUS実施に向けた共同検討を開始|北海道電力株式会社
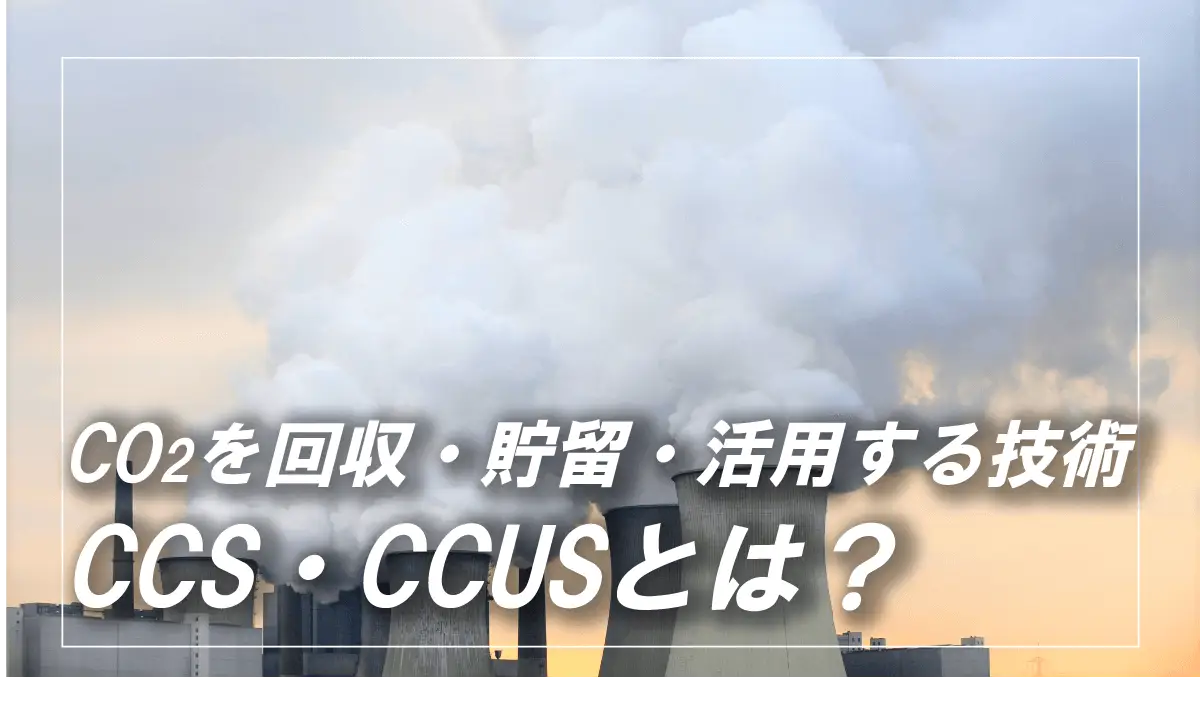
日揮ホールディングス×コスモ石油×レボ・インターナショナル
日揮ホールディングス、コスモ石油、レボ・インターナショナルの3社は、持続可能な航空燃料(SAF)の製造に向けて包括的な取り組みを展開しています。この取り組みの特徴は、家庭から出る使用済み食用油(廃食用油)を効率的に回収し、SAFの原料として活用する点です。これにより、限られた化石燃料資源の消費を抑えつつ、二酸化炭素排出の削減が可能になります。
具体的には、大阪府内5施設のイオンモールに家庭系廃食用油の回収ボックスを設置し、一般家庭からの廃食用油を効率的に回収する体制を整備。回収された廃食用油はレボ・インターナショナルが収集し、製造施設まで運搬します。その後3社で共同設立したSAFFAIRE SKY ENERGY(サファイヤ スカイエナジー)が回収した廃食用油からSAFを製造します。
この取り組みは、廃棄物の有効活用とカーボンニュートラルの実現を同時に達成する先進的な事例です。また、地方自治体(堺市)との連携により、より効果的な資源循環の仕組みを構築している点も注目に値します。従来、廃食用油は廃棄されるケースが多かったところ、本プロジェクトを通じて有効活用することで、環境負荷の低減に貢献しています。
参考:堺市と廃食用油の SAF 等への資源化促進に関する協定を締結ー大阪府内5施設のイオンモールに家庭系廃食用油の回収ボックスを常設ー|日揮ホールディングス株式会社
複数社でカーボンニュートラルの取り組み効果を最大化するための3つのポイント

ここからは、複数社でカーボンニュートラルの取り組み効果を最大化するための3つのポイントを紹介します。
各社の経営層が積極的にコミットする
1つ目は、各社の経営層が積極的にコミットすることです。経営層のコミットメントにより、組織全体での取り組みへの理解が深まり、現場レベルでの実行力も高まります。また、各社で優先順位や削減目標が異なることを考慮し、事前に以下の3点を明確にすることも重要だといえるでしょう。
● 協業の目的と期待される効果
● 最終意思決定者の設定
● 各社の役割分担
特に、同業他社や異業種との連携においては、相互理解を深めた上で、リスクや成果を公平に分配できる体制を構築する必要があります。経営層主導で協業の基盤を整えることで、カーボンニュートラルの取り組み効果を最大化していきましょう。
報告・検証の仕組みづくりをおこなう
2つ目は、効果的な報告・検証の仕組みづくりです。
まず、GHGプロトコルなどの排出量算定基準を各社で共通化し、削減効果を数値で比較・評価しやすい環境を整備します。
次に、定期的な進捗確認と改善のサイクルを確立します。四半期や半期ごとに進捗状況を報告し合い、目標達成に向けた課題を共有した上で、必要に応じて修正計画を立案したり、新しい施策を検討したりすることでPDCAサイクルを回していきます。
その際、各社の機密情報の管理と情報開示のバランスも重要です。そのため、NDA(秘密保持契約)を締結し各社の機密情報を保護する必要があります。その上で、必要な範囲で社外や投資家に情報を公開すれば、ステークホルダーからの信頼を失うことなく、協業を進めることが出来るでしょう。
各社が持つ技術を組み合わせて共同開発する
3つ目は、各社が持つ技術を組み合わせて共同開発することです。設備投資や研究開発リソースを共同で負担する体制を構築することで単独企業では実現が困難な新技術開発や大規模実証が可能になります。
また、複数の企業が参画することで、投資負担を分散できるメリットもあります。これにより、より大規模かつ多角的な実証実験や技術開発も実現しやすくなります。
共同開発を成功させるための注意点として、開発された技術の特許や使用権の取り扱いを事前に明確化することが挙げられます。権利関係を適切に調整することで、新市場の開拓や事業規模の拡大につながり、より大きな環境負荷削減効果を生み出すことが期待できるでしょう。
まとめ
今回の記事では、カーボンニュートラルの実現に向けて企業ができることや複数社による共創の実例、効果を最大化するためのポイントまで詳しく解説しました。
サステナビリティハブでは、他にもカーボンニュートラルに関する記事を公開中です。是非あわせてご覧ください。




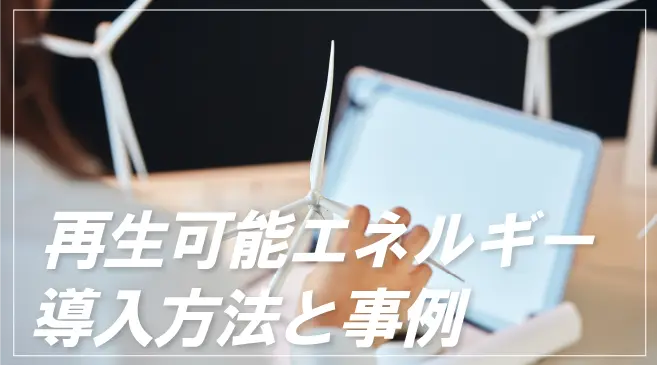


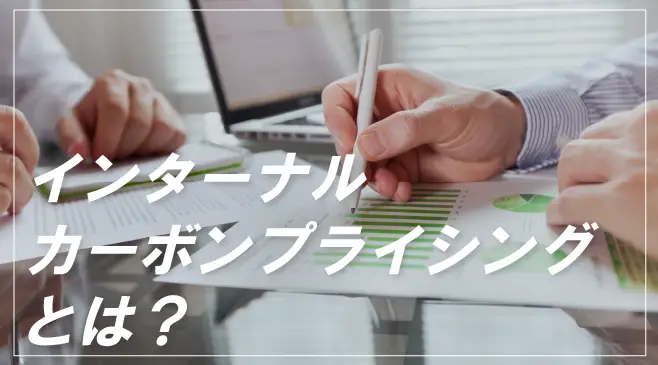
COMMENT
現在コメントはございません。