前編【プラント建設の未来を支える技術者たち #03】回転機のエキスパート

目次
海外におけるプラント・施設の設計・調達・建設(EPC)を事業の柱とする日揮グローバルでは、幅広い分野の技術エキスパートが事業の根幹を支えています。彼らの持つさまざまな専門技術はプラント建設だけでなく、サステナブルな社会を実現するうえでも欠かせないものです。 そこでサステナビリティハブでは、チーフエンジニアの方々に専門技術や最新トピックなどをお伺いしながら技術知識を深めていく、新しい連載をスタートしました。第3弾となる今回のテーマは、「回転機」。是非ご覧ください。(インタビュアー:サステナビリティハブ編集部)
* エキスパート制度は、日揮ホールディングス、日揮コーポレートソリューションズ、日揮グローバル、日揮が対象
* チーフエンジアは、チーフエキスパートとリーディングエキスパートの総称
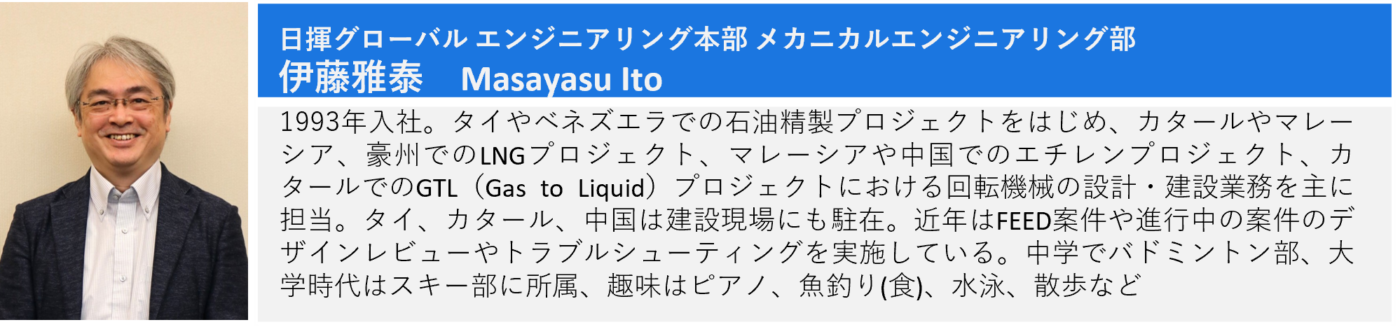
「回転機」とは?
回転機の種類
――初めに、伊藤さんが専門にされている「回転機」とはどのような機械なのか、教えていただけますか。
回転機というのは簡単に言うと、「動力につないで回転の力を使って気体や液体を動かす機械」のことです。
例えば身近なところでは、ヘアドライヤーも回転機の一種。これは、電力を動力源にして内部の羽根を回転させて空気を送っているわけです。
これまで意識したことはないかもしれませんが、私たちの身の回りには必ず気体や液体などの流体があり、流体があるところには必ず回転機があります。道の栓をひねれば水が流れてきて、換気扇を回すと空気が流れていくのは、どこかにポンプや送風機といった回転機があるからです。このように僕らの文明的な生活は、実は回転機の存在の上に成り立っているんですよ。

プラント内での回転機の活用事例
――なるほど、私たちは日常生活で回転機からかなりの恩恵を受けているんですね。ではプラント内部では、どのような回転機が使われているのでしょうか。
プラント内部で使われている代表的な回転機としては、送風機、圧縮機(コンプレッサー)、ポンプが挙げられます。これらは流体を輸送する主目的を果たす被駆動機です。被駆動機に動力を与える方は、駆動機と呼ばれてタービン、ピストンエンジン、電動機が挙げられます。駆動機と被駆動機を繋いて動かすと目的が果たせます。少しややこしいですが、発電機というのは電動機と同じような機械ですが被駆動機でありタービンやエンジンで駆動されます。
「送風機」・「圧縮機」はどちらも気体を輸送する機械で、送風機のイメージは気体を輸送するだけ、圧縮機は気体を圧縮して輸送するというイメージでしょうか。また、「ポンプ」は液体を輸送する機械です。
身の回りで大きな回転機を見かけることはないと思いますが、例えば大型LNGプラントで使う圧縮機は、何十メガワットという出力となり、先ほどお話したヘアドライヤーの約何万倍の出力になります。それくらい大きなものを扱っているんだなと考えていただくと分かりやすいかもしれません。
回転機は言うなれば〝プラント稼働中に動いている機械全般″です。つまり、回転機が止まるとプラントの稼働も止まってしまいます。それくらい重要な機械だという意味で、回転機は「プラントの心臓部」や「プラントのエンジン」と言われます。
回転機の最新技術・トレンドとは?
――近年、エネルギー分野における脱炭素に向けた動きが加速していますが、回転機の分野では、どのような動きがあるのか教えていただけますか。
トレンド①:圧縮機の動力源の脱炭素化
1つ目は、LNGプラント内の圧縮機の動力源として、従来の蒸気タービンやガスタービンに代わり、電動機(電気モーター)の採用が検討され始めていることです。
LNGプラントでは、非常に大きな圧縮機を使って、天然ガスを冷やすために冷媒となるガスを循環させているのですが、これまではガスタービンを使って圧縮機を駆動させていました。LNGプラントは天然ガスが産出されるガス田の近くに設置することが多いのは、その豊富な天然ガスを燃料にしてタービンを回すことが出来るからです。ところが、天然ガスを燃焼するとどうしてもCO2を含む排気ガスが出てしまうことから、ガスタービンの代わりに電動機で圧縮機を動かそうという流れが出てきています。

――LNGプラント内の圧縮機の動力源を、電気に置き換えようという流れが生まれているのですね。これに関して、伊藤さんのチームではどのような対応をしていますか。
ガスタービンから電動機への置き換えの検討が進む中で、高出力電動機をプラントに適用する際の諸問題・課題が各方面から報告されています。例えば、可変速機から発生する高調波による機械側への影響、冷却水設備が必要であること、モジュール建設との組み合わせでは鉄骨基礎設計に困難が伴う可能性などが課題として挙げられます。
課題解決に必要な技術は、すべてが新技術というわけではありませんが、これらを総合的に組み合わせてエンジニアリングすることはまだあまり浸透しておらず、ある意味“新技術”と捉えて良い分野だと考えています。そこで、各方面から報告されている事例や課題に常に目を光らせ、設計力を継続的に高めることで、お客様に最適なソリューションをご提案できるように備えています。
トレンド②:メーカー各社による水素用の圧縮機の開発
2つ目は、CO2を排出しない「水素エネルギー」活用に向けて、回転機メーカー各社が水素を圧縮するための圧縮機の技術開発を進めていることです。
これはどういうことかというと、例えば、今は料理をする時にガスコンロの点火スイッチを押すとガスが出てきますよね? そういう風にスイッチ1つで水素がどこでもだれでも使えるような時代が来るかもしれないと想定した時、水素を各家庭やビル・工場まで配管を通して送る必要が出てきます。そして、そのために必要となるのが「圧縮機」です。
現時点でも、すでに水素を圧縮する機械はありますが、大流量の水素圧送に対応できる圧縮機には開発の余地が多々あります。今後、今の都市ガスのようにもし水素が一般的に使われる世の中になると、大流量の水素を送り続ける必要が出てくるため、それに対応できる圧縮機の開発が期待されているのです。
水素圧縮の注目点の一つとして、水素はガス分子量が極めて小さいため、遠心力を使った圧縮技術では空気や酸素などのように簡単に圧縮できないという事があります。しかし大流量を扱うとなると遠心圧縮機でなければならないというのが、水素の圧縮が難しいとされる所以です。この課題を打開すべく、メーカー各社が開発を始めており、我々エンジニアリング会社を含む関連業界は、クリーンエネルギーとしての水素の普及予測動向を横目で見ながら、遠心圧縮機開発動向に注目しています。
――水素エネルギーが普及した未来を見据えて、メーカー各社が大流量の水素の輸送に耐えうる圧縮機の開発を進めているわけですね。実際には、どのような研究開発が進んでいるのでしょうか。
遠心圧縮機というのは、遠心力で気体のスピードを上げることを利用して圧縮するのですが、水素の音速の速さを利用して気体の流速を極限まで上げることができれば、従来よりも効率的に圧縮することができます。というのも、水素の音速は空気の約4倍と極めて速いので、従来の技術は水素から見ると4分の1までしかガス流速が上げられていないというわけだからです。
もし流速をあるレベルまで上げることができれば、これまでの遠心圧縮機技術では直列2台の圧縮機が必要だったところを1台の圧縮機でまかなえる、といったことが可能となります。とはいえ、ガスの速度だけで限界設計をすると、今度は機械側が持たなくなる。この二つの課題をどうにかできないかということをメーカー各社が試行錯誤しているわけです。
我々は圧縮機を製造しているわけではないので、この技術を直接的に生み出したり獲得したりすることにはなりません。ですが、この新技術がプラントエンジニアリング・建設に適用可能という技術査定ができれば、プラントの敷地面積縮小や運転信頼性の向上をプラントオーナーにご提案できます。そうした意味でも、最新技術や各社の開発状況をくまなくチェックし、日々アップデートに励んでいます。
回転機エンジニアの仕事とは?
プラント建設における回転機エンジニアの仕事・必要な知識
――プラント建設の中で、回転機エンジニアはどのような仕事をしているのでしょうか。
プラント建設における回転機エンジニアの仕事は、大まかに3つのフェーズに分けられます。プラント建設の計画段階では、そのプラントに必要とされる動機械の選定予測をして、プラントの基礎設計を固めるための支援をおこないます。
次に建設開始に際して、機械購買の技術支援を実施します。発注後には発注された機械をプラントに組み込むインターフェース詳細設計をおこないます。これは、機械の土台基礎、配管、電源ケーブル、計器など、その機械との接続が必要となる技術部門との設計調整を指します。メーカーに発注する機械は基本的にカスタムメイドになりますから、国内外のメーカーの拠点に足を運んで詳細を決める必要があり、この時期には出張が多くなりますね。
プラント竣工後は、試運転に立ち会うこともありますし、プラント運転時のトラブルシューティングをおこなうこともあります。
――回転機械についてだけでなく、関連する幅広い知識が必要とされそうですね。
そうですね。いわゆる“機械屋さん”として必要とされる、一般機械工学、熱力学基礎、流体工学基礎、材料力学基礎、振動工学基礎などに加えて、ビジネス経験からしか得られない、機械を製作する過程の知見や機械を運転・保全する知識が必要となります。 さらに、機械は電動機(電気モーター)や計器類を一つにパッケージ化して取り扱われるので、電気工学やパッケージ計装の知識もある程度必要となってきます。

回転機エンジニアの腕の見せ所は?
――回転機エンジニアの業務は非常に多岐にわたりますが、特に“腕の見せ所”だなと感じるのは、どんな時でしょうか?
実は回転機屋さんの本当の腕の見せ所は、FEED*やPre-FEED*でいかに適切な機械選定ができるか、という基礎設計の部分だと思っています。EPC*のフェーズではすでに機械のタイプや台数が決まっていることがほとんどですが、実際に購入準備する段階になって、「これでは成立しません」とメーカーさんに言われてしまうケースもあるんです。そんな時は、初期設計から携わって回転機エンジニアのスキルや知見を活かすことが出来ていれば、と歯がゆく思うこともあります。
*FEED:Front End Engineering and Design。概念設計・FS(Feasibility Study)の後におこなわれる基本設計のこと
*Pre-FEED:FEEDの前段階の概念設計・概算費用検討のことで、FSの前におこなわれる
*EPC:Engineering(設計),Procurement(機材調達),Construction(建設)の頭文字を取った略称で、プラントエンジニアリングでおこなわれるコア業務
EPCのフェーズでは、トラブル時の原因究明をうまくできるかどうかが、回転機エンジニアの腕の見せ所といえます。Eにおいてトラブルはインターフェースの設計に関する事、製作中に予期せず起きてしまうトラブルもあります。また、回転機は動くモノなので、設計通りに作っても、工場で試運転をしても、どうしても現地の運転でトラブルが起きてしまうものなんですよね。一番多いのが「好ましくない高振動が起こる」ケースですが、振動の原因は一つではなく多岐にわたります。そこで、色々な可能性を挙げて刑事ドラマさながらに一つ一つアリバイをつぶしていく必要があるのですが、これが本当に大変です。
技術伝承・人材育成のポイントとは?
――回転機の最新トレンドのところでお話しいただいた技術開発に加えて、技術伝承・人材育成もチーフエキスパートの重要な業務だと伺いました。技術伝承・エンジニア育成において、特に大事にしていることはありますか?
技術伝承においては、経験を書き留める事が大切だと思っています。私自身の技術だけではなく、日々の業務の中で発生したトラブルも含めて発見を書き留めてシェアする仕組みを数年前にチームメンバーとともにつくりました。ここに報告される最終技術の査定を私自身がおこない、メンバーの経験から得られる材料に私の持っている味付けをすることによって、技術伝承を試みています。
人材育成については、学卒で配属となる新入社員を除き、会社は教育する場ではないととらえています。こちらから教え込むのではなく、課題に直面した時に自ら考え、分からないときは遠慮なく聞きに来て欲しい。それが自然と出来るように、風通しの良い職場環境を作るよう心がけています。
また、海外関連会社のエンジニア育成については、中堅エンジニア数名とともに特定のトピックについての講義・議論を実施し、彼らのスキルアップを図っています。
まとめ
今回の記事では、「回転機」のチーフエキスパートに、専門技術や最新トピックスなどに ついて話を聞きました。インタビュー後編の次回記事では、仕事のやりがい、回転機のチ ーフエキスパートとして活躍するに至った経緯や、休みの日の過ごし方など、プライベー トに近い内容をお伺いします。
