後編【プラント建設の未来を支える技術者たち #03】回転機のエキスパート

目次
海外におけるプラント・施設の設計・調達・建設(EPC)を事業の柱とする日揮グローバルでは、幅広い分野の技術エキスパートが事業の根幹を支えています。彼らの持つさまざまな専門技術はプラント建設だけでなく、サステナブルな社会を実現するうえでも欠かせないものです。 そこでサステナビリティハブでは、チーフエンジニアの方々に専門技術や最新トピックなどをお伺いしながら技術知識を深めていく、新しい連載をスタートしました。
回転機のチーフエンジニアへのインタビュー後半の本記事では、キャリアパスや転機となった出来事、プライベートの過ごし方などについて話を聞きました。(インタビュアー:サステナビリティハブ編集部)
* エキスパート制度は、日揮ホールディングス、日揮コーポレートソリューションズ、日揮グローバル、日揮が対象
* チーフエンジアは、チーフエキスパートとリーディングエキスパートの総称
回転機の概要や最新トピックスなどについて聞いたインタビュー前半は、こちらの記事をご覧ください。
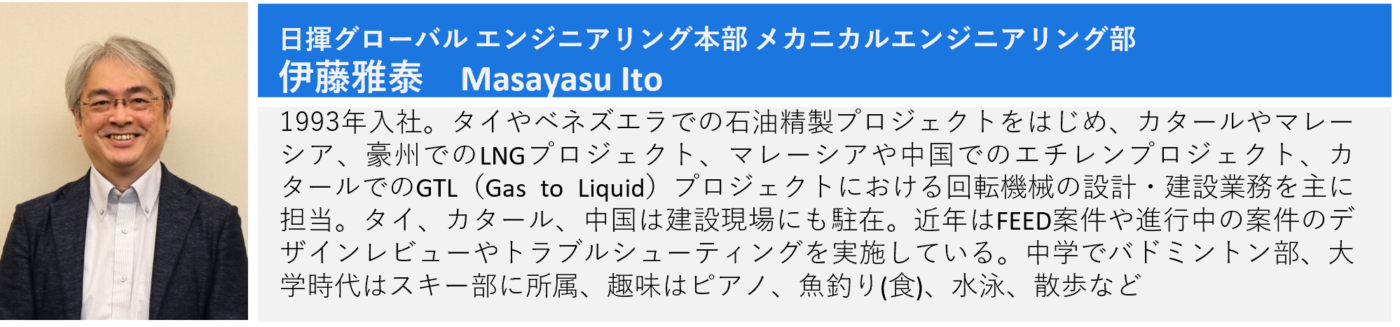
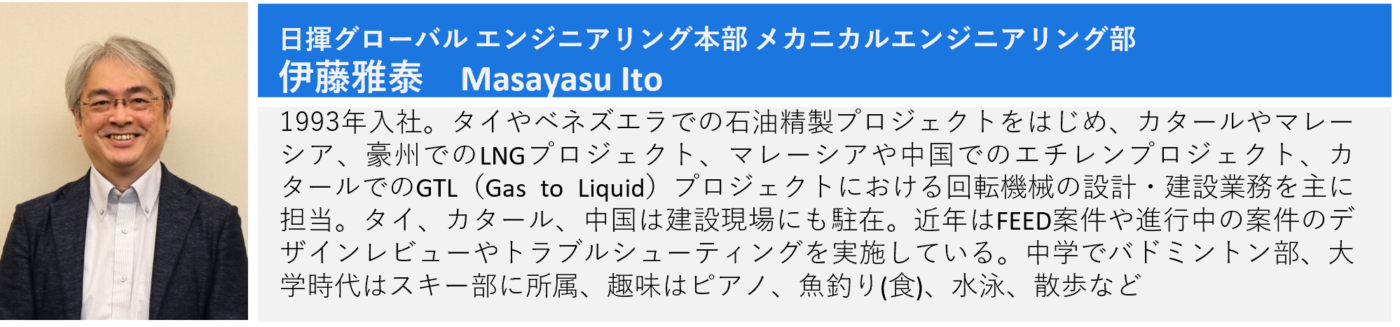
回転機エンジニアとしてキャリアを築く
ゼロから回転機エンジニアに
――伊藤さんはエンジニアとして20年以上のキャリアをお持ちですが、入社後はどのような経緯で回転機のエンジニアになったのでしょうか。
入社して新入社員研修を受けた後に、機械設計部門に配属されたのが全ての始まりです。この配属先は想定外だったので、非常に驚きました。というのも、私は鉱山学科が母体の研究室出身で機械とは全くの無縁だったからです。用意された自分の名刺を見たら「回転機」と書いてありましたが、回転機の意味が分からない、そんなスタートでした(笑)。
今、周囲にいる後輩エンジニアは大学で機械工学を学んできた人がほとんどなので、当時の私と比べて、最初から予備知識をしっかり持って業務に当たっていることに感心しますね。


――全く予備知識のない分野の仕事をすることになって、最初はかなり戸惑われたのではないでしょうか?
はい、全てを手探りで進めているような状態でしたから、本当に大変でした。とにかく上司からやれと言われたことを追いかけるだけで精一杯。まともに仕事ができるようになったなと感じたのは10年くらい経ってからで、それまでは、分からなさすぎて辞めたいと思ったことは何度もありました。
――それでも続けることができたのには、何か理由がありましたか?
配属されたからには、回転機について一通り出来るようになるべきだという思いが、第一にありました。何とか喰らいついて学んできた中で、入社10年目に中国のプラント建設現場に2年近く駐在することになり、その時の経験が、エンジニア人生のターニングポイントになりました。
通常、回転機エンジニアの仕事は設計するところまでなのですが、その建設現場では、専門外の工事も、計画からすべて任されてしまい、転職した心づもりで日々仕事をしました。さらに予想もしていなかったのは、“その道30年”というような強者たちが、据付屋、振動解析屋というように細分化された専門家として客先から現場に駐在していたことです。彼らと対峙して工事を進める事にとても苦労しました。
ですが駐在後半には客先からも信頼を得られ、専門家集団からは工事から運転に至るまでの一連の流れの中で様々なことを学ぶことができました。また、数々のトラブルシューティングを経験し、回転機というものを総合的に扱う専門家として大いに自信がつきましたし、この苦労の末、客先に当社の回転機屋のプレゼンスを示すことができた達成感も得ることができました。大抵の事は一人でハンドリングできるようになり、「自分の腕で稼いでいる」という感覚が生まれたのも、この頃です。
――現場駐在で苦労しながら仕事に向き合い続けた経験が、エンジニアとして大きく成長するきっかけにもなったのですね。
そうですね。そのあたりからお客様と対等に話が出来るようになってきて、お客様が「よくやった!」と褒めてくれたり、トラブルを一緒に解決できたりすると、面白いなと思うようになりましたね。そこからは、飛躍的にスムーズに知識が付いてくるようになりました。
メーカーとユーザーをつなぐ存在として
――現場で得られた回転機の知識は、その後の業務でどんな風に役立ちましたか。
回転機エンジニアの設計業務は、極論を言ってしまえば、現地に行かなくてもできる仕事ですが、現場を知っていると設計がもっと面白くなるんです。現場では、お客様サイドから来ているオペレーションやメンテナンスのプロの方々から話を聞くこともできます。彼らは、我々が横浜オフィスで仕事をしているだけでは絶対に知りえない知識を持っていますから、そういう人と対等に話を出来るようになってくると、どんどんこの仕事が面白くなりますし、仕事の深さにも違いが出てきます。
据付の際には、機械と動力源とをシャフト同士でつなぐのですが、その際、それぞれのシャフトが運転状態で同一線上に並ぶよう、位置を調整する「芯出し(アライメント)」という作業が必要になります。
芯出しの状態が悪いと、設備の振動が大きくなって、部品が破損したり設備の寿命が短くなったりするので、芯同士のズレを100分の1mmの単位で調整します。大型回転機の重さは数十トンにもなるので、持ち上げたりずらしたりするのも簡単ではありません。それを、最終的に髪の毛一本程度のズレに抑えて揃えるわけですから、本当に大変な作業です。何度も据付工事に立ち合ってきたので、今では自分でも作業員に指示できるくらいまで分かるようになりました。このような事を体と頭で覚えると、回転機の中の部品の構成、その形状に至るまで理解が深まり、この理解は設計にも生きてきます。


――伊藤さんが理想としているエンジニア像はありますか。
我々のようなプラントエンジニアリング業界における回転機エンジニアというのは、回転機という機械パッケージを製作供給するメーカーと、それをプラントで運転するユーザーとを技術力でつなぐプロであると思っています。簡単なことではありませんが、メーカーともユーザーとも対等に技術の話ができるスキルを持つ、つまり広く深い知見を貪欲に取得することを継続するというのが、私が目指すエンジニア像です。特に、顧客であるユーザーの方々に頼りにされる人材というのが理想ですね。
プライベートの過ごし方
――出張の多いお仕事とのことですが、ワークライフバランスはとれていると感じますか?仕事と家庭の両立において、特に意識していることはありますか。
そうですね、最盛期にはメーカーへの出張で海外を飛び回っていましたが、最近はそこそこバランスの取れた生活が出来ていますよ。定期的に実施している人間ドックでは、歳を重ねたなりの好ましくない数値も現れているので、あまり無理をしない事を心がけてはいます。
――プライベートの時間はどのように過ごしていますか。最近の関心ごとや、趣味などがあれば教えてください。
家にいる時は、昔からの趣味でピアノを弾いて遊んでいます。ピアノは小学校の頃から習っていて当時はクラシックを弾いていたんですが、どうにも面白くなかったんです。大学に入ったときにジャズの真似事を始めて、それ以来ずっとジャズを中心に、楽しみながら弾いています。
学生の頃まで魚釣りが好きで、家の近所の沼から始まり、大学生になってからは海や川へと車を走らせて、よく釣りに出かけていたのですが、就職を機にすっかりやらなくなっていました。また釣りをしたいなと最近よく思うので、そろそろ再開したいですね。
今後の展望
――最後に、回転機のチーフエキスパートとしての今後の目標や、回転機エンジニアの方々に伝えたいことがあれば教えてください。
当社はプラント建設計画の初期における基礎設計役務をあまり受注しませんが、そこにも回転機エンジニアのスキルが必要とされる場面が多々あるため、そういう設計を手掛けたいと常々思っています。
また、これはあまり知られていないことかもしれませんが、回転機を専門とするエンジニアの数は少なく、世界のエンジニアリング業界では非常に貴重な存在です。社内では当たり前のように回転機エンジニアがいるので、そう感じる機会は少ないかもしれません。ですが、回転機屋さんというのは非常に大事なエンジニアだということはお客さんサイドがわかっていますから、海外のお客さんとも堂々と渡り合って、自信と誇りをもって仕事をして欲しいと思っています。
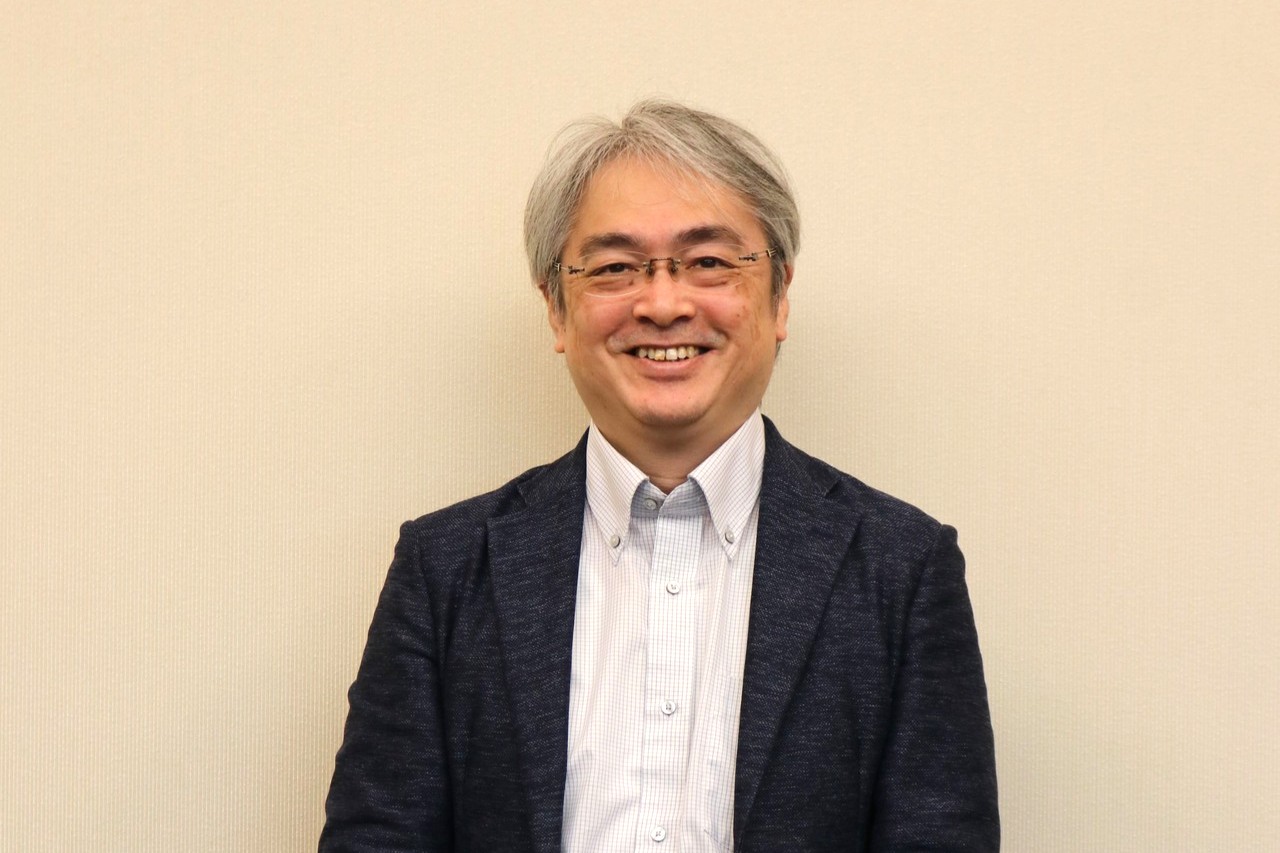
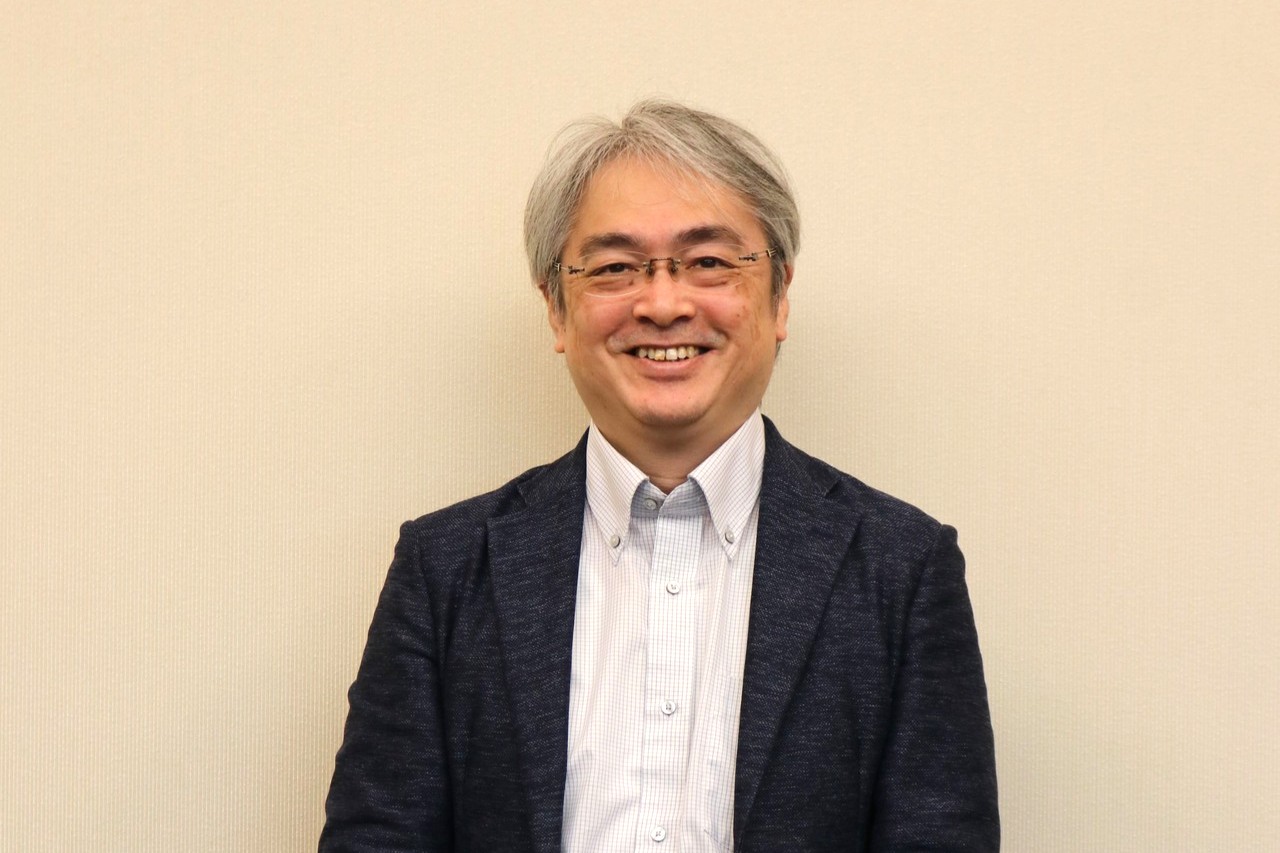
まとめ
今回の記事では、「回転機」のチーフエキスパートとして活躍するエンジニアに、キャリアパスや転機となった出来事、プライベートの過ごし方などについて話を聞きました。回転機の概要や最新トピックについて聞いたインタビュー前半は、こちらの記事をご覧ください。

